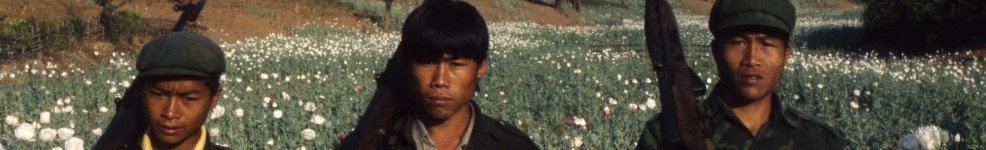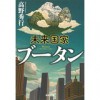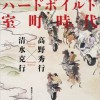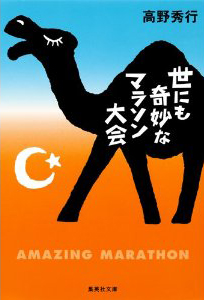歴史は水で割るべからず
公開日:
:
最終更新日:2013/02/05
高野秀行の【非】日常模様
 ゲストハウスのそばのソイ(路地)で、カバーにムエタイのポスターをびっしり貼った屋台を見かけた。
ゲストハウスのそばのソイ(路地)で、カバーにムエタイのポスターをびっしり貼った屋台を見かけた。
最近、若者にはとんと人気がないと言われているムエタイだが、庶民のとくにおじさん世代には
まだまだ熱い人気を誇っているらしい。
☆ ☆ ☆
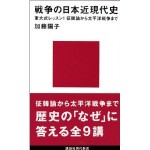
加藤陽子『戦争の日本近現代史 東大式レッスン!征韓論から太平洋戦争まで』(講談社現代新書)は、
実に魅力的な本だった。
なにしろ前書きに、「この本は、研究書を水割りにしたような概説書ではありません」と書いてある。
さらに強調するに、
「やさしく言い換える過程で、いわば水割りを薄めすぎたりすると、研究書や論文が、その生命として本来もっていたはずの視覚の切れ味も失われてゆき、ついには、たとえば、高等学校で使っていた日本史教科書などを単に詳しくしただけのものになってしまうおそれがあると思うからです」
思わずグッと来てしまった。まだ冒頭の段階だが、ここで一つ重要なことがわかる。
加藤先生は相当な酒飲みにちがいない。
酒を水で薄めすぎたときの悲しさをこれ以上適確にかつ美しく表現した文章を私は知らない。
まさに「その生命として本来もっていたはずの視覚(味覚)の切れ味が失われてゆく」というしかないのである。
しかも冒頭のいちばん重要な部分に酒の比喩をもってくるという感覚。
酒を飲まない人、酒のことがよくわかっていない人には絶対できない。
ここで私は不遜ながら加藤先生を「同志」と認定してしまった。
その後は同志先生の講義を拝聴するばかりだが、中身もよかった。
宣言通り、話は水割りでなくストレートあるいはロックでガツンガツン進む。多少なめらなでない部分もあるが、口当たりなど気にせずガチガチ行く。
明治から太平洋戦争にかけて、日本の政府・軍・国民が、みんな、「国際法」と「条約」の遵守に懸命になっていたという意外な事実に驚いた。
行け行けどんどんで戦争に向かっていたわけではなく、あくまで「自分たちは国際的に正しい」という理論武装にやっきになっていたのである。
またそこには、常に「自衛権」が頭にあり、侵略・侵攻への意志と自覚は奇妙なほど薄かった。「このままではロシアやアメリカにやられてしまう」ということばかり考えていたようだ。
日本は昔から今までずっと「被害者意識」で来ているのかもしれない。
だが、正直言って、日本近代史に疎い私には半分くらいしか理解できなかったので、メコンウィスキーのストレートでもやりながら、再読したいと思う。
関連記事
-

-
新連載はまさか、あの…?!
『アジア新聞屋台村』本日発売!…なのだが、なんか、今回もまた売れない予感がしてきた。芥川龍之介ではな
-

-
ミャンマーがハリウッドになった!?
『ミャンマーの柳生一族』で、「ローマの休日」をパクッた武田鉄矢主演の映画「フォトグラファー・アンド・
-

-
孤高の伝道者・大槻ケンヂ
昨年暮れ、つまり10日あまり前にアップされた音楽関係サイトで、大槻ケンヂのインタビューが載っている
-

-
ヒマラヤのイエティは神戸で飼育されていた!?
最近、さまざまな未知動物について調べているが、 私が知らなかったことがすごくたくさんあり、 驚きの毎
-

-
『メモリークエスト』続編決定
二日酔いのまま、笹塚で杉江さんに会って、定例の放談会。 本の雑誌社の女性スタッフが、『メモリークエス
-

-
またプロレスの話ですが
三沢光晴の一件について長らく考えていたが、結局「三沢は死んでいない」という結論に達した。 「彼は俺
-

-
バトルロイヤルに負ける
7月に紀伊国屋新宿本店で行われていた書店員オススメ本バトルロイヤルだが、 「ゴッドファーザー」の続編
-

-
あなたの本職は何ですかと訊かれた
3月に、大野更紗さんが「わたくし、つまりnobady賞」という謎の文芸賞を受賞し、 私もその授賞式
-

-
他社の本を宣伝する出版社って…
今注目を集めているポプラ社の文芸ウェブサイト「ポプラビーチ」をたまに眺めているが、 いろいろな意味
- PREV :
- ソマリの海賊に実刑判決!
- NEXT :
- タイの懐メロを熱唱してしまう