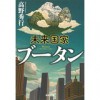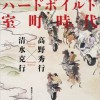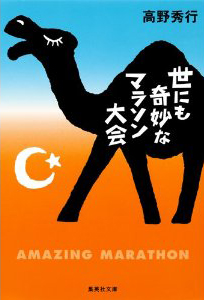僕が、落語を変える
公開日:
:
最終更新日:2012/05/28
高野秀行の【非】日常模様

私は自分のことを「文芸人」だと思っている。
文章を芸とする芸人であるという自覚だ。
だから、「芸人」の話にはすごく興味がある。
落語家の話はとくに興味深い。
落語家は芸人だし、一人ですべての世界を創るという部分も文芸人に共通している。
それから落語は、出版業界にとって、斜陽産業の大先輩でもある。
一時期ラジオの普及で全盛期を築きながらも、テレビの普及でどん底に落ち込んだ。
そして今は、メジャーでないのに人気はあるという微妙な地位をきずいている。
柳家花緑や立川談春、志らくだって一般の人がどれくらい知っているのか疑問だが、
独演会のチケットはとるのが難しい。そこだけ見れば超売れっ子なのだ。
私たちが目指すところもその辺かもしれないと思う。
なんてわけで、柳家花緑+小林照幸『僕が、落語を変える』(河出文庫)を興味深く読んだが、一つまったく関係ないところに引っかかった。
先代・小さんによれば、戦前は落語家がしゃべり終わっても拍手がパラパラ程度しか起きなかったという。
拍手は戦後になってからで、「アメリカ人が教えたのか?」と小さんも言っていたそうだ。
花緑は「落語はかつてテレビみたいなものだったんじゃないか」とも言っている。
だから「口」に「新しい」=「噺(はなし)」という字をあてたのだろう、と。
テレビやラジオに人は拍手をしないから、落語家(噺家)にも拍手をしなかったのかもしれないという解釈だ。
ちなみに、「落語家」か「噺家」かという議論があるらしい。
談志は「落語家」だと主張しているという。
本書ではあまり踏み込んでないからよくわからないが、
「オチ」優先が「落語」で、「新しい情報」優先が「噺家」なのだろうか。
こういうのも“同業者”としてはひじょうに興味深く、参考になる。
関連記事
-

-
高島俊男先生の人生は失敗だったらしい
敬愛する高島俊男先生の新刊『お言葉ですが…別巻⑤ 漢字の慣用音って何だろう?』(連合出版)を読む。相
-

-
勝利の方程式も崩れるときはある
丹沢・大山登山の翌日は予想通りというか、足が激しく筋肉痛。 トレランの鏑木さんに影響されて、山を駆
-

-
世界一の辺境・日本で活動します
ほんとうは4月初めからソマリランド&ソマリアに行く予定だったが、 今回の大震災でキャンセルすることに
-

-
だからアメリカは嫌なんだ!
今、バンコクであります。 今回、フライトがノースウェスト航空。9.11以来アメリカの飛行機に乗るのは
-

-
エンタメ・ノンフ座談会
火曜日、『本の雑誌』の特集で座談会に参加。 テーマは「緊急座談会 エンタメ・ノンフの棚を作れ」。 私
-

-
ゾウ本あらため辺境中毒!
すっかり忘れていたが、今週の20日(木)に『辺境中毒!』(集英社文庫)が刊行される。 『辺境の旅は
-

-
絶滅動物の生き残り?
さて、マリンダはいったいなにものなのか。 既知の現生哺乳類にはこんな動物はいない。 ところが、過去に
-

-
『わが盲想』の意外な落とし穴
いよいよアブディン『わが盲想』(ポプラ社)が本日発売である。 宮田珠己部長には前もって献本
- PREV :
- イスラムと仏教
- NEXT :
- 「世にも奇妙なマラソン大会」見本入手