空気?よむ必要なしの神々続出〜「口語訳 古事記」
公開日:
:
最終更新日:2012/05/25
つれづれ日記
打ち合わせの後、ふと時間が空いたので丸善&ジュンク堂に入る。
本当は時間調整のつもりで入っただけなのに、気がつけば本を手にし、ページを繰っている。
買うつもりがなくても買わされてしまうのが、ジュンク堂の恐ろしいところだ。
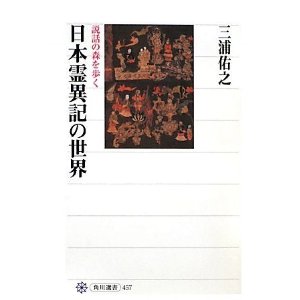 新刊を一とおり眺めた後、サブカル棚、ノンフィクション棚をざっと見ながら振り返ったら「古典」の棚があった。本とは、まことに出会いだなと常々思うけれど、一発目に手にした三浦佑之著「日本霊異記の世界 説話の森を歩く (角川選書) 」が当たりだった。
新刊を一とおり眺めた後、サブカル棚、ノンフィクション棚をざっと見ながら振り返ったら「古典」の棚があった。本とは、まことに出会いだなと常々思うけれど、一発目に手にした三浦佑之著「日本霊異記の世界 説話の森を歩く (角川選書) 」が当たりだった。
日本霊異記は平安時代初期に書かれた、仏教説話集。
全3巻、漢文で書かれているものの、中身はさまざまな話を交えながら、仏教の教えをやさしく説いていくというもので、要するに難しい仏教の中味を市井の人々にも分かりやすいようにかみ砕いた書物である。
著者はこの日本霊異記に書かれた内容を、当時の日本の文化や風習など時代背景まで丹念にたぐっており、説話に込められた真意や、現在の我々ではすんなりと納得できないギャップを埋めてくれる。
あまりに面白かったので奥付を見てみたら、「口語訳 古事記」で第1回角川財団学芸賞とある。
古事記といえば、日本霊異記より更に100年近く前、西暦712(和銅五)年に書かれたとされる、日本最古の歴史書だ。
ユーキャンの「日本の名山」や、NHKのテキストで戸隠神社の宿坊について書いた時、わんさか出てくる神々の名前や由来について、大量の資料を集めてあれこれ調べたことがある。
それらはすべて古事記や日本書紀にも登場する神々でもあり、この2冊はいずれ読んでみたいと思っていた。
しかし、原文は漢字の羅列であり、直訳したものは時代背景などが違いすぎて非常に読みにくい。
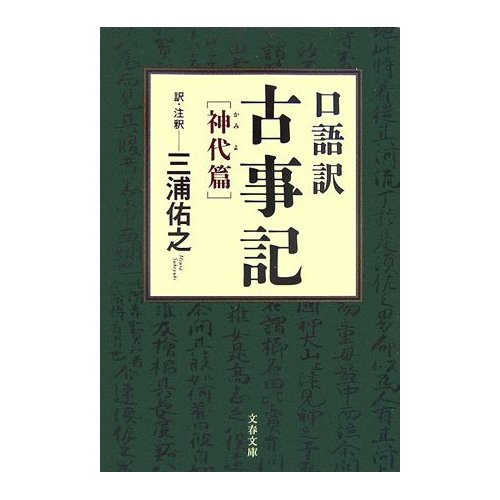 ところが、三浦祐之氏が書いている「口語訳 古事記」は、本のタイトル通り、我々が普段喋っている言葉で書かれており、なおかつ、古老が語って聞かせるというスタイルなので非常に分かりやすい。しかも、各章ごとに詳細な注釈がついていて、意味不明な神様の名前、唐突に展開するストーリー、つじつまの合わない言動などが逐一分かるようになっている。
ところが、三浦祐之氏が書いている「口語訳 古事記」は、本のタイトル通り、我々が普段喋っている言葉で書かれており、なおかつ、古老が語って聞かせるというスタイルなので非常に分かりやすい。しかも、各章ごとに詳細な注釈がついていて、意味不明な神様の名前、唐突に展開するストーリー、つじつまの合わない言動などが逐一分かるようになっている。
歴史書は、時の治世者や制度の都合などによって、物語の改編や、エピソードの追加などが行われている可能性もあり、その辺りの推測と、なぜそうなったのかという類推が注釈に綴られているのも読む側としてはうれしい。
色恋や嫉妬、自己中で自由奔放な“神様”たちの立ち振る舞いもさることながら、「ノド」という言葉が、当時は「ノミド(飲み戸)」“飲む入り口”と書かれ、後に2文字に縮まったことなど、当時の言葉が現代にも息づいていたり、姿を変えて残っていることを知るのもこの本の醍醐味だろう。
PR
関連記事
-

-
手帳はデジタル?それともアナログ?
一昔前なら、首標のタイトルは 「手帳はシステム手帳?それとも綴じ手帳?」 といったところだと思
-

-
つい、作ってしまった〜イチゴのショートケーキ
先日、ツイッターで紹介した 「@nifty:デイリーポータルZ:プロに教わる超美味しい家ケーキのコ
-

-
「ニセコ〜峰延」180km。踏破の記録
道中タオルを巻いていたため、おでこの真ん中に日焼けのラインがついてしまった小林です。(歩き旅の道中、
-

-
久しぶりに聞いたこの言葉ー「ぼんたん」
今年もまた謎の演奏団体Say Noの季節がやってきた。 Say Noとは「練習数回で金賞を狙う」とい
-

-
ジューンブライドと、ミャンマーの「黒」デューサー
高校の同期、従兄弟、6月に入って結婚式が相次ぐ。 用事があって出席できなかったが、大学の後輩も10年
-

-
冬ソナ終わりました…(T.T)
「冬のソナタ」 つっこみ入れつつ結局、最後まで見てしまった。 しかし、最終話ユジンのあのズラ(ヴ
-

-
時差ボケというより、ボケ老人?
火曜日の早朝、成田着。 気温5度。 温度差25度の洗礼をもろに浴びた。。。 マレーシアでは日
-

-
12分の1が終わろうとしている・・・
いまごろですが、明けましておめでとうございます。 年明けから、次の番組テキストの作業がスタートし





