新趣味はロマ(ジプシー)音楽
公開日:
:
最終更新日:2013/04/16
高野秀行の【非】日常模様

最近、急に趣味がいくつもできてきた。
その一つがロマ(ジプシー)音楽を聞くこと。
ジプシー音楽とはセルビアで出会って強く心を動かされ、その後もエミール・クストリッツァの映画を
繰り返し観ながら魅了されていったのだが、
ソマリランド本が出て、ぱったりと仕事が途絶えたところに、決壊したダムのごとく、私の生活になだれ込んできた。
ジプシー音楽の凄さは、誰が聞いても楽しい娯楽音楽でありながら、
プロとして他ジャンルの音楽家も文句のつけようのない高度な技術をもち、
そして核心部には魂があるということだ。
ある意味、私の理想でもある。
もちろん、そんな能書きはあとからついてきたことで、
純粋に音楽に聴き惚れてしまっている。
土地柄もいい。
セルビア、ルーマニア、マケドニア、アルバニア、ブルガリア、ハンガリー、トルコ、ギリシア、など
バルカン半島から中東にかけてが「メッカ」なのだ。
そして「趣味」としてなによりいいのは、もうすでに日本人で先達が存在することだ。
関口義人がその人で、『ジプシー・ミュージックの真実』(青土社)はすごい本である。
最初手に取ったとき、巻末に「厳選ディスクガイド100」と書いてあったとき、「どうかしてるよ」と思った。
ジプシー・ミュージックだけで”厳選して”100もあるなんて多すぎると思ったのだ。
しかし、本書を読みつつ、自分で買ったCDを聴いていくと、100という数字がいかに少ないものかわかってきた。
ジプシーが住む国はヨーロッパ圏内だけでも軽く10を超える。
それぞれが独自の音色や楽器編成をもつうえ、ブラスや弦楽器主体、アコーディオンやツィンバリン(鉄琴みたいなもの)など
実にいろんな形態がある。インストロメンタルもあれば、歌もある。
そんなの厳選しても500枚くらいは必要なのではないかと思うようになり、すっかりオタクの道に入っている。
もっとも私はまだ入門篇でうろうろしているに過ぎず、CDを買うたびに、関口先生の本をガイドブック兼辞典として
開いている。
この本は音楽だけでなく、現在ジプシーの人々がどんな暮らしを送っているのかについても深く探った貴重なルポだ。
帯には「世界でも類のないドキュメント」とあり、前に紹介した大内治『タイ・演歌の王国』(現代書館)もそうだったが、
日本人のオタク的パワーは大したものなのである。
関連記事
-

-
「困ってる人」書籍化プロジェクトX
私がプロデュースしている大野更紗「困ってるひと」の連載もそろそろ最終回近い。 いよいよ書籍化の相談を
-

-
2011年のベスト本はもう決まった!
数日前、増田俊也『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』(新潮社)を読了した。 これほど面白くて
-

-
略して『みらぶ~』!
『未来国家ブータン』の3刷りが届いた。こんな表紙である。すげ~なあ。 本書を「みらぶ~」と命名
-

-
私の名は「ヒダヤットゥラー高野」
昨日のカロメに続き、連日のサプライズである。 数日前、在日外国人関係の取材で、在日パキスタン協会の
-

-
2013年小説ベストワン決定
風邪は治ったものの今度は咳がひどく、声もがらがら。 とくに夜になると咳が止まらず苦しい。 朝
-

-
元キャバ嬢&風俗嬢にはかなわなかった
「SPA!」の掲載誌が届いた。 「イスラム飲酒紀行」はかなりトンチキな企画で(文芸誌ではできない)、
-

-
インディアンの驚くべき小説
シャーマン・アレクシー『はみだしインディアンのホントにホントの物語』(小学館)という本を妻の本棚で
- PREV :
- 呆然
- NEXT :
- 元「たま」の石川浩司氏とトークイベントのお知らせ



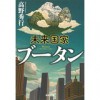
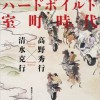





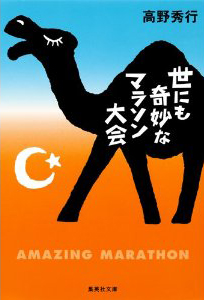

Comment
ロマ語などという、これまた高野先生の好きそうなマニアックな言語もありますよね。
グジャラート語あたりがルーツだということはわかっていながら、各地に分散しているために方言の比較研究もまだまだ進んでいません。
中東~中央アジア各地にも「ロマニ」を自称とする民族集団が点々と存在していていずれも「音楽」を生業としており、ルーツについては研究者ですら「馬車に乗って続々とインドからやってきた」などとありえないことを書いていますが、個人的にはトルコの軍楽隊の末裔だと考えています。
トルコ人たちが中央アジアから移動してくる際に、当時すでに精緻を極めていたインド音楽に触れ、その楽士たちを大量に引き連れながら西へ西へと進んでいき、バルカンから撤退する際に取り残された人々ではないでしょうか。それまでトルコ人貴族らに養われていた楽士たちが土着化し、結婚式などの演奏で食い扶持を稼ぎ始めたのだと考えられます。
ルーツのところではサンタルの音楽などともつながっているのでしょう。
トルコの軍楽隊がヨーロッパの古典音楽に多大な影響を与えたことは言うまでもありませんが、フラメンコのルーツでもあり、最近お気に入りのIndialuciaは、「フラメンコとインド音楽の1000年ぶりの邂逅」です。
http://www.youtube.com/watch?v=zReP15usQ3I
私も詳しいわけじゃないですが、ロマの言葉はどうやらグジャラート語よりヒンディー語に近いみたいですね。
でも、”水”が「パーニー」とか、サンスクリット系の単語はかなり保持してるので
ちょっと驚きました。
ロマがトルコの軍楽隊の末裔だとすると、起源はそんなに古くないってことですよね。11世紀か12世紀。言語がかなりしっかりインドの特徴を残しているところや、各地のロマの言葉がまだかなり似通っているのを見ると、妥当なところかもしれません。
とはいっても、日本でいえば平安時代末期から鎌倉初期。大昔ではありますが。