クリント・イーストウッドとモン族
公開日:
:
最終更新日:2012/05/28
高野秀行の【非】日常模様

一年ぶりにTSUTAYAでDVDを借りて、観た。
ウチザワ副部長がかつてブログで絶賛していたクリント・イーストウッドの
「グラン・トリノ」。
頑固で超保守の白人老人が、インドシナ難民(モン族)二世の若者と
友情を育むという話。
「アメリカの本質」をエンタメのパッケージにきちんと収めた
ひじょうに良質な作品だった。
「ザ・ラスト・カウボーイ」という題名でもよかったのではないか。
ところで、映画のストーリーとは関係なく、
「モン族」がアメリカでこんなことになっているのかというのに驚いた。
モン族は中国では「苗族」、タイでは「メオ」などと呼ばれているが、
自称はHmong(モン)。
ラオスでは70年代、CIAに協力させられ、ケシ栽培=アヘン生産を行ういっぽう、
反共産ゲリラ用の兵士にされた。
そのため、ラオスの共産党政府から弾圧を受け、
大量の難民がタイに出た。
やがて、モン難民は欧米にも出て行った。
私がチェンマイにいたとき、モン族を研究する人が二人いて、
一緒に難民がつくった村に行ったこともあるが、
アメリカやフランスで育ったモンの男性がよく嫁探しに訪ねてくるという話を聞いた。
欧米では、女性はあっという間に新しい環境になじみ、
アメリカやフランスの価値観になっていくのに、
男は古いモンの気質や習慣が抜けないため苦労し、
また欧米化したモン女性と結婚できなくて
わざわざ教育も受けていない「古き良きモン」を探しに来るといっていた。
そういえば、別の機会に知り合いになった安井清子さんという東京外大でモン語を教えている人がいるが、
たしかアメリカまでモン難民のその後を追いかけていたと聞いたことがある。
今度会ったら、「グラン・トリノ」で描かれるモンはどれくらい現実に近いのか
訊いてみたい。
関連記事
-

-
テレビ川柳師・ナンシー関の秀逸な評伝
読書運というものがあって、読んでも読んでも面白い本に当たらないときもあれば、手にする本がことごとく面
-

-
米軍による驚くべき支援
28日(月)調布市被災者支援ボランティアセンターの手配で、被災地の特養老人ホームに物資を届けるという
-

-
「倒壊する巨塔」は訳が素晴らしい!
ローレンス・ライト著、平賀秀明訳『倒壊する巨塔』(白水社)を読んだ。 素晴らしい本だった。 「イス
-

-
対談は仕事場でなく家庭で
宮田珠己さんとの対談シリーズ「タカタマ対談」の第5弾を 本の雑誌の杉江さん立会いの下、 関東某所に実
-

-
落語界の奇才、小説もいけるのか!
春風亭昇太がリーダー役を務める創作話芸アソーシエーション、略してSWA。 私は昇太さんの独演会も好き
-

-
講談社ノンフィクション賞の最終候補になった
以下のようなことになったそうです。 -----------------------------



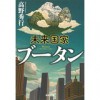
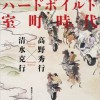





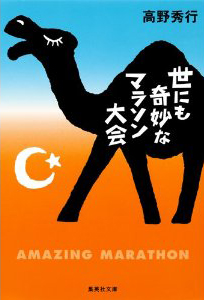

Comment
AGENT: DoCoMo/2.0 SH02A(c100;TB;W24H16)
モン族といえば、Van Pao将軍のラオス政府転覆未遂事件が思い出されます。二年くらい前の話ですが、元CIAのアメリカ人が協力して武器を運ぼうとしていましたね。