趣味は仮説
公開日:
:
最終更新日:2012/08/13
高野秀行の【非】日常模様
私は仮説を立てるのが趣味である。何かを見たり聞いたりしたとき、「これはもしや××とつながるのでは?」とか「これがあの○○の原因なのでは?」と思いを巡らす癖がある。
たいていの場合、全くの見当違いだったり、とっくの昔に誰かに発見されていて実はもう世間の常識だったりするのだが、まあ、そういうことを考えるのが好きなのである。
先日も阿部謹也の『ハーメルンの笛吹き男』(ちくま文庫)を読んでいて興味深い記述に出会った。
13世紀のドイツでは、市民権を持っている商人が二種類いたという。大規模な商業活動を営む大商人と通常の市内小売りしか許されない小商人である。
大商人はなんでも扱えるのだが、小商人の扱えるものはひじょうに限定されている。
1353年の規定だと、「脂肪、バター、ベーコン、チーズ、乾葡萄、イチジク、蜜、蝋、塩漬あるいは燻製の魚など」となっているらしい。要するに日常生活に欠かせない基本食品のみということになる(パン屋と肉屋はまた別の分類だったらしい)
こんな差別がなんと19世紀まで続いていたという。
「これは!」と私の仮説脳がときめいた。「ヨーロッパの軽減税率の起源はここにあるのかも!」
軽減税率とは、生活必需品(主に食品)のみ税率を低くおさえるというものだが、日本でも議論されているように線引きがひじょうに難しい。
ていうか、どう考えても無理である。基準が何一つない。
でも、ドイツでは19世紀までこのような「差別」がきちんとあった。つまり、必需品とそうでないものを分ける基盤があり、そこから延長していけば
分類は決して不可能でなかったし、国民にもすんなり受け入れられたのではないか。
てな「仮説」を思いついた。もちろん、ドイツだけにしか当てはまらない話かもしれないし、逆に経済学や歴史学の世界ではすでに常識かもしれない。
誰かに話したくてしかたないのだが、妻は私が日々繰り出す莫大にして無意味な仮説群にうんざりしているようなので、「そうだ、ブログに書けばいいんだ!」と思い当たった。
原稿にするためには、きちんと調べないといけないし、わざわざそんなことをする暇もない。ブログはその点、きちんとした文章を書く必要もなく、
仮説がまちがっていれば、読んだ人が教えてくれる可能性もあり、うってつけだ。
ブログとはもしかすと仮説を書くためにあるのかも!…というのが、今日新しく得た仮説である。
関連記事
-

-
あなたの本職は何ですかと訊かれた
3月に、大野更紗さんが「わたくし、つまりnobady賞」という謎の文芸賞を受賞し、 私もその授賞式
-

-
バトルロイヤルに負ける
7月に紀伊国屋新宿本店で行われていた書店員オススメ本バトルロイヤルだが、 「ゴッドファーザー」の続編
-

-
人生の内定がとれてないアナタに
内澤副部長の名作ポップはコレ。 副部長の漫画イラストなんて見たことがない。お宝ものだ。 ス
-

-
元キャバ嬢&風俗嬢にはかなわなかった
「SPA!」の掲載誌が届いた。 「イスラム飲酒紀行」はかなりトンチキな企画で(文芸誌ではできない)、
-

-
Somaliland ni iru hutari no watashi
Twitter dewa mou kaiteirukedo,yatto Somaliland
-
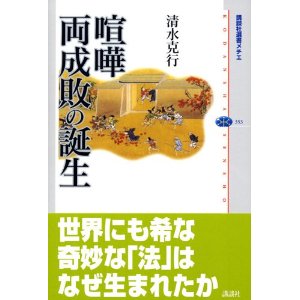
-
日本の中世人と現代ソマリ人の共通点と相違点
『謎の独立国家ソマリランド』の感想を述べたツイートに、清水克行『喧嘩両成敗の誕生』(講談社選書メチエ
- PREV :
- ソマリランドで発見した素敵なドリンク
- NEXT :
- 日本のゲバラ、ここにあり。

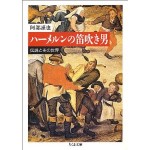


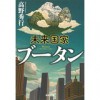
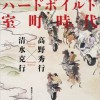





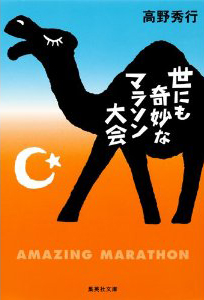

Comment
…オチが全てを物語ってます!仮説は立証され難い、と云う仮説を思い付きました。