闇の王国ブータン
公開日:
:
最終更新日:2013/04/30
高野秀行の【非】日常模様
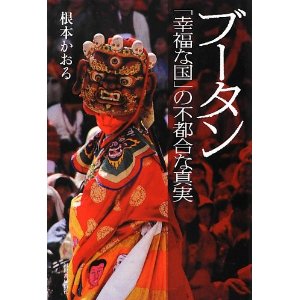
ぜひ多くの人に読んでほしいと思いつつ、こちらの気持ちの思い入れが強くてなかなか紹介できなかった本を2冊。
まずは根本かおる『ブータン「幸福の国」の不都合な真実』(河出書房新社)。
ブータンが抱える最大の問題点はネパール系難民について、ひじょうに細かく記している。
著者はUNHCR(国連難民高等弁務官)事務所の所長としてブータン難民の支援にあたっていた。
さらに本書ではブータン国会の議事録まで読み込んでブータン政府側の気持ちの移り変わりを描いていて
説得力がある。
ただ、難民発生の具体的な状況は今ひとつよくわからない。
10万人という莫大な数の難民が内戦もないのに発生したというのは尋常ではない。
学校や診療所が閉鎖されたとか、「手練手管の嫌がらせ」を受けたなどとあるが、今ひとつ具体的な事例に欠ける。
ブータン政府がよほどうまいこと住民の心理を操って、出て行かせたのかもしれない。
中には「一時的に避難しよう」とか「仕事もないしちょっと出稼ぎにネパールに行こう」と国を離れた人もいたかもしれない。
また、ただでさえ混乱し人々が疑心暗鬼に陥っている難民キャンプで、難民個人個人の国外脱出事例を聞き出すのは難しいだろうし、
そもそもブータン国内ではそんな取材や調査はできない。
まさに「ブータンの闇」だ。
ブータンは今でもゾンカ語を話すチベット系ブータン人にとってはひじょうに良い国だと思うし、
政府もよくやっていると思うが、
そうでない人たちに対しては非情としか言いようがない。
ブータン王国がいかに人工的に創りあげられた国なのか痛烈にわかる。
拙著『未来国家ブータン』と併読すれば、光と闇の部分がはっきりするのだが、ため息がでる。
もう一冊はうってかわって格闘技。和良コウイチ『ロシアとサンボ -国家権力に魅入られた格闘技秘史』(晋遊舎)。
うってかわってと言いつつ、こちらも「国家」の話になってしまう。
ソ連がいかに国家主義のもとに、サンボの基礎をなした「柔道」を消し、ソ連各地の格闘技を取り入れながら
国技としてのサンボを創りあげていったかが資料をもとに丁寧に明かされる。
「サンボ」という名称が付けられたのは1938年。
「来たるべき戦争に備え、国防の訓練が求められていた時代である。
そのために、格闘技という手段は、肉体的にも精神的にも申し分の無いものであった。
それだけではない。一億人を超すロシア人のような大民族から一千人に満たない少数民族まで、
多様な民族で構成されたソビエト社会主義共和国連邦に、一枚岩のナショナル・アイデンティティが求められていた時代でもある」
それが「各民族の格闘技の良いところを結集したソ連生まれの新しい格闘技」のサンボだったという。
1938年とは面白い。
なぜなら、同じく”民族格闘技”であるタイ式キックボクシングも「ムエタイ」と名付けられたのは1939年頃なのだ。
ムエタイのほうはもともと「ムエ・コラート(コラートの格闘技)」とか「ムエ・チェンマイ(チェンマイの格闘技)」などと各地方の名前で呼ばれていた格闘技を総合し「ムエタイ(タイの格闘技)」と名付けたのだ。
当時、愛国主義を強烈に打ち出していったピブーン政権下で行われた。日本が明治時代に「大相撲」を創ったようなものだ。
大相撲が「国技館」をつくったように、タイでも「ラチャダムナン・スタジアム」という”国技館”を作った。
(以上は、日本唯一のムエタイ研究家にして本人自ら格闘家でもある平成帝京大学の菱田慶文先生の論文「ムエタイの賭博化変容」による。)
ソ連とタイでは国の体制や状況は全然ちがいつつも、同じ時期に「国技」が国策として創られたわけだ。
「比較民族格闘技学」とか、誰かやってくれないものだろうか。
きっとおもしろいと思うのだが。
関連記事
-

-
『困ってるひと』ついに発売
大野更紗『困ってるひと』(ポプラ社)がついに発売となった。 今アマゾンで見たら、180位である。
-

-
ナカキョーの文庫解説に感激
西芳照『サムライブルーの料理人』(白水社)を読む。 サッカー日本代表専属でワールドカップにも2回帯
-

-
ビールで放射能が保護できる!!
「しん」さんという人のコメントでサイトを開いたら、 こんな記事があった。 なんとビールが放射線を保
-

-
酒飲みにやさしいイスラム国
半年間のトルコ遊学から帰国して間もない慶応大学の学生S君にトルコの話を聞いた。 場所は阿佐ヶ谷の
-

-
79人はちと多いのでは…?
上智大学の講義は、先週、実質的に第一回目で マレーシアでジャングルビジネスを営む二村聡さんにお越しい
-

-
エンタメ・ドキュメンタリー
フジTVの『フジテレビ批評』という番組に出演した。 テーマは「エンタメ・ノンフとエンタメ・ドキュメン
-

-
見えないサッカー世界大会
昨夜、ギリシアより帰国。 行きも帰りも飛行機に乗っている時間(トランジット含む)が24時間を超えると
- PREV :
- 求む、ナイスな雑木林コース
- NEXT :
- 『謎の独立国家ソマリランド』PVはこちらで



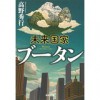
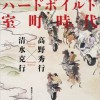





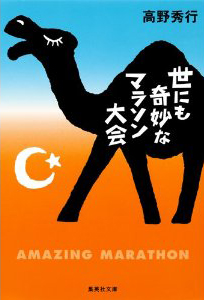

Comment
シッキムはかつてネパール系住民の増加でレプチャ人が少数劣勢になり、戦後インドに組み込まれることになりました。かの地のネパール人は最初はイギリス人が茶畑労働者としてつれてきた人々でしたが、戦後はインド政府が領土的野心からネパール系をシッキムに送り込んだ、とも考えられるのではないでしょうか。
(別にネパール系でなくてもいいような気もしますが、山岳地帯の暮らしに慣れてる、ということなのでしょうか)
ブータンにもこれと同じことがおきているのかどうかは分かりませんが、90年代までのブータンはほぼ完全な鎖国状態でしたから、ネパール系住民を追放するためにかなり荒っぽい手段もとられていたのでは…と思います。それを実証することは難しいのですが、シッキムしかり、北隣のチベットしかり、庇を貸して母屋を取られていった隣国を見て来たブータンにとっては、異民族の追放は国是だったのかも知れません。
サンボ本の副題はsamozashchita bez oruzhija(武器なき護身術)で、へー、と思ったんですが、これの略称がsamboだったんですね。
私の認識もHUさんとほぼ同じで、シッキムの轍を踏むなという観点から難民を受け入れない、あるいは弾圧するという行動も止むを得なかったのではないかと。
それにブータンの同化政策を受け入れたネパール系住民はけっこういますし。
えこひいき(あるいは身びいき)も大分入っちゃってますけど…。
>huさん、
>ajiketoさん、
「やむを得なかった」と私も思おうとしてたんですけどね、本書を読むと考えが変わりますね。
10万人が国外追放で難民生活を余儀なくされたということは重いですよ。
ブータン政府も同化政策をちゃんとやっていなかったようだし、かなりヒステリックに異民族追放に走ったような印象を受けます。
まあ、読んでみて下さい。
「竜馬が行く」ファンが「実は坂本竜馬はそれほど剣が強くなかったのが史実」なんて言われてもどうしても受け入れられないのと一緒で…。
頑張って読んでみます(笑)。