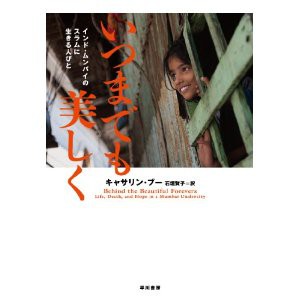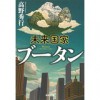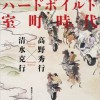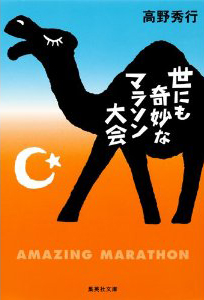ここ数年最大の問題作か?
公開日:
:
最終更新日:2014/02/03
高野秀行の【非】日常模様
キャサリン・ブーの『いつまでも美しく インド・ムンバイのスラムに生きる人々』(早川書房)を読んだ。
ここ数年、こんなに引っかかる小説を読んだ記憶がない。
この十年あまり、一般では「傑作」として評価・絶賛されている本で、私が「いや、問題作でしょ?」と異論をはさみたくなった本といえば、ノーベル文学賞を受賞したクッツェーの『恥辱』(ハヤカワepi文庫)と「本の雑誌」で1990年代のベストワンにえらばれたオースン・スコットカード『消えた少年たち』(ハヤカワSF文庫)が双璧である。
二作ともとても手放しで褒めるような本ではない。
「こんな本、アリか?」と眉をひそめたくなった。
かといって単純に批判の対象としたくなるわけでもない。
誰かと議論したくなるような小説である。
そして、面白いかどうかと言われれば、やっぱり面白い小説だ。
そして、今回の『いつまでも美しく』もそのラインにつながる。
(なぜかこれも早川書房だ。ハヤカワは問題作の好きな出版社なんだろうか?)
一昨日、この本について書こうとしたのだけど、難しすぎてやめてしまった。
自分の言いたいことを過不足なく読者に伝えるなら、何日もかかってしまうからだ。
私が感じた問題点をまとめるなら、
1)これはノンフィクションと言えるのか?
2)取材方法に問題がありすぎなのではないか?
3)結局、世界の頂点に君臨する人間が世界の最底辺の人々からさらに搾取しているだけではないか?
ということになる。
ただ、一流の問題作とは簡単に答えが出るものではない。
もしこれらの疑問がすべてイエスだったとしても(私はそうだと思うが)、
この本が存在するかしないかで言えば、存在すべきだと思ってしまう。
本書は小説として読んだとしてもひじょうに面白い。
(むしろ、「事実を元にした小説」だったら問題作ではなく普通に傑作だっただろう)
インドの最下層の人々をこんなにリアルに描いた本は読んだことがないし、
心をゆすぶられるのも間違いない。
読者のみなさんがこれを読み、各々で考えてみてほしいと思う。
ひじょうに有意義ですごく面白い読書体験になることはまちがいない。
関連記事
-

-
メモリークエスト締切り間近!
最近すっかりブログでの案内を忘れていたが、 web幻冬舎で連載中の企画「メモリークエスト」は まだ依
-

-
ヒマラヤのイエティは神戸で飼育されていた!?
最近、さまざまな未知動物について調べているが、 私が知らなかったことがすごくたくさんあり、 驚きの毎
-

-
可哀想なレビュアーの話
角田光代の『紙の月』(角川春樹事務所)を読んでから、アマゾンのレビューを見た。 「駄作です」という
-

-
島国チャイニーズと沖縄系ブラジル人
読了してから時間が経ってしまったが、野村進『島国チャイニーズ』(講談社)は 万人にお勧めの良書であ
-

-
イスタンブールは遠い…
再び成田空港に行き、今度はちゃんと飛行機が飛んだ。 が、ドバイに着いたものの、日にちがずれたためイ
-
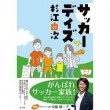
-
携帯電話が故障中&ここ数年でベストのサッカー本
携帯電話が帰国直後に突然壊れてしまった。 いつもなら慌てて修理に走るところだが、これまで2ヶ月
-

-
『ワセダ1.5坪青春記』、出版間近?!
『ワセダ三畳青春記』の韓国語版カバーなるものが集英社から送られ、驚く。 マジで出版する気らしい。
-

-
となりのツキノワグマ
ツバルが沈まなくて驚いたばかりだが、 またしても環境問題の常識が覆される本を見つけた。 宮崎学『と
- PREV :
- 英国人の見たSMAP
- NEXT :
- 第3回梅棹忠夫・山と探検文学賞を受賞しました